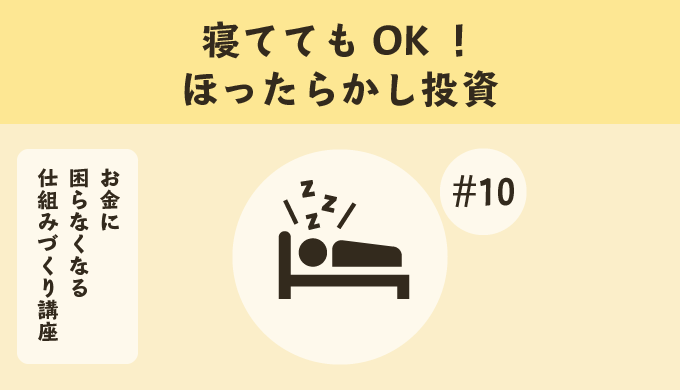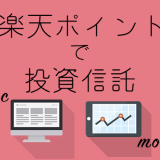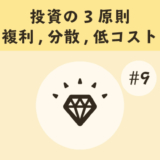この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
「投資初心者は『3つの基本』を押さえよう!」という前回の記事では、
- 貯蓄型保険は、コスパの悪い投資
- 投資の基本→複利、分散、低コスト
- 全世界分散投資がおすすめ
と、投資の基本をお伝えしました。
まだお読みでなければ、ぜひお読みください。
投資初心者は『3つの基本』を押さえよう!
さあ、「お金に困らない仕組みづくり講座(全10回)」も番外編をのぞけば今回でおしまい。
最終回となる今回は、公務員が不労所得を得るための投資術をお届けします。
公務員は放ったらかし投資がオススメ
公務員の方は本業があるので、投資にあまり時間をかけられません。
なので、一度設定したらある程度放ったらかしにできるやり方が良いです。
具体的には、「積み立て投資」がオススメです。
積立投資=先取り貯金の投資バージョン
毎月一定額を投資に回して、長期で運用する方法です。
一度設定すれば、自動で積み立てられていくので楽チンです。
この講座の5回目で紹介した「先取り貯金」の投資バージョンというイメージでOK。
積立期間が長いほど複利効果(前回参照)が強力に働くので、少額でもいいのでとりあえず始めてみると良いでしょう。

それでは、積み立て投資ができる方法を紹介します。
イデコがおすすめ第一候補
イデコ(個人型確定拠出年金)は、所得がある方ならオススメしたい投資制度です。
2017年から公務員も利用できるようになりました。
たとえば、
- 年収600万円の方が、
- 月12,000円をイデコで運用すれば、
- 年間で約30,000円くらい税金が安くなる
このように、自分の資産を作るために運用してるだけなのに、税金が安くなるのがイデコの特徴です。
将来受け取る時に課税されるケースもあるので、受け取り前には専門家に尋ねるなど、出口戦略は持っておくほうが良いと思います。
イデコのメリットとデメリット

それぞれ見てみましょう。
- 所得控除で税金が安くなる
- 運用時の儲けに税金がかからない
- 受け取る時にも税制優遇がある
- 60歳まで使えない
- 手数料がかかる
- 運用リスクを負う
イデコのメリット・デメリットについては、「公務員専用イデコ活用マニュアル」でも詳しく解説しています。
とくに、公務員は掛金の上限が低いにもかかわらず手数料は一律という、「公務員ならではの注意点」もあったりします。
無料メルマガに登録していただいた方にマニュアルをプレゼント中なので、ぜひお受け取りください。
イデコをまだ始めない方が良い人は?
節税メリットがあるイデコですが、「何が何でも始めるべき」ではありません。
あくまで投資なので、余裕資金で行うべきです。
たとえば、「公務員になったばかりでまだ貯金もほとんど無いよ…」という方はまず先取り貯金から始めましょう。
また、若手の方だったら自己投資にお金をかけたほうが、人的資本も高まり、人生の充実度も向上するかもしれません。
高卒公務員の方からいただいた質問に答えた記事がありますので、あわせて読んでみてください。
イデコの口座はSBI証券がおすすめ
イデコで積み立て投資するには、「イデコ専用口座」が必要です。
銀行や証券会社で作ることができますが、おすすめは「SBI証券」です。公務員専門FPである僕自身もSBI証券でイデコを運用してます。
理由は2つです。
- 管理手数料が無料
- 選べる商品のバリエーションが豊富
手数料無料が良いというのはお分かりですよね。「商品バリエーション」について補足します。
前回もお伝えしたように、投資の基本は「分散投資」です。
もしイデコ口座で株式しか選べなかったら、偏った投資になってしまい、分散投資ができません。なので、商品のバリエーションは豊富な方が良いです。
SBI証券なら、債券や株式、その他金融商品とバリエーションがとても豊富なので、しっかり分散投資が可能です。
低コストな「セレクトプラン」を選ぼう
また、SBI証券のイデコは「セレクトプラン」と「オリジナルプラン」の2つから選ぶようになります。
特段の理由がなければ、低コストな「セレクトプラン」を選びましょう。
セレクトプランは2018年11月から導入された新しいプランで、低コストな商品がラインナップされています。
僕がイデコ口座を作った当初は、まだ「セレクトプラン」は無く「オリジナルプラン」しか選べなかったんですが、今ではちゃっかり「セレクトプラン」に乗り換えてます。
イデコは長期運用になりますので、低コストが基本ですからね。

ネット証券ならではの手数料の安さも魅力です。まずは資料請求してみましょう。
公式サイト
ロボアドバイザー
AI(人工知能)が勝手に投資してくれる「ロボアドバイザー」という投資サービスがあります。
自分で投資するより手数料が高めですが、「投資の本を読んで勉強してみたけど、踏み出せない…」という方にとってはアリかもしれません。
「手数料は確実なコスト」なので、基本的にはロボアドではなく、低コストのインデックスファンドを自分で選ぶことをオススメしてます。
また、ロボアドだと利益に税金がかかりますが、NISAやイデコなら非課税です。この点でもやはり自分で運用する方が良いですね。
ロボアドバイザーの手数料は高め
たとえば、スマホ一つで投資可能な「ウェルスナビ」というサービスがあります。
ウェルスナビの手数料は積み立て資産の1%(年率)で、これ以外の手数料は無いので、シンプルなところは評価できます。
でも、やっぱり高いんですよね。
自分で投資すれば、手数料0.1%台のインデックスファンドもあります。
見かけ上の手数料の違いはわずかでも、積み立て資産が増えるほどコストの差は大きくなってきます。
つみたてNISA
長期の積立&分散投資を支援するために、2018年から始まった国の制度です。
ふつう、運用で利益がでた場合、約20%の税金がかかるところ、つみたてNISAで運用すると、この税金がゼロになります。
- 年間40万円まで投資できる
- 最長20年間積み立て投資可能
- 選べる商品が厳選されている

とくに、商品が厳選されているのは大きな特徴ですね。
選べる商品が厳選されている
つみたてNISAで選べる金融商品は、「超低コストで、長期の運用に向いたものにしないとダメ!」と国が基準を作ってます。
そもそもそんな商品は少ないので、商品選びもラクです。
裏を返せば、自由度が低いと言えますが、投資初心者にとっては投資対象が多すぎても混乱するだけなので、「貯蓄から投資へ」を目指す時代の制度としてはアリだと思います。
つみたてNISA専用口座をつくろう
つみたてNISAで運用するには、専用口座が必要です。
口座開設はもちろん無料なので、ぜひ作っておきましょう。僕自身はSBI証券でNISA口座を持ってます。
ネット証券の最大手なので安心して使えると思いますよ。
公式サイト
また、楽天証券も使いやすいですね。
つみたてNISAの口座は一つの金融機関でしか作れませんが、投資をするための証券口座はどの証券会社でも作れます。
楽天証券もネット証券なので手数料も安く、後述するポイント投資もできますので、僕も使ってます。
つみたてNISAの口座の開設で悩んだら、SBI証券か楽天証券で問題ありませんよ。
公式サイト
その他:ポイント投資
積み立て投資ではありませんが、楽天ポイントを使って投資ができます。
ポイントなら気軽にできる方も多いと思いますので、余ってる楽天ポイントがあればやってみましょう。
楽天ポイントでの投資方法を、スマホとPCの画面付きで詳しく説明してます。
まとめと番外編

これで「お金に困らない仕組みづくり講座(全10回)」はおしまいです。
- 公務員は放ったらかし投資でいこう
- まずは「イデコ」から
- ロボアドは手数料に注意
- つみたてNISAで長期運用
- ポイント投資も試そう
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
全10回の講座でお届けした内容は、お金の知識の根幹部分です。
枝葉のテクニックはもちろんありますが、根っこや幹がしっかりしてないと、大きな果実は実りません。
基本をしっかり押さえて、資産を増やしていきましょう。
このブログでは、お金についての知識やお役立ち情報を引き続き発信していきますので、ぜひまた遊びに来てくださいね。
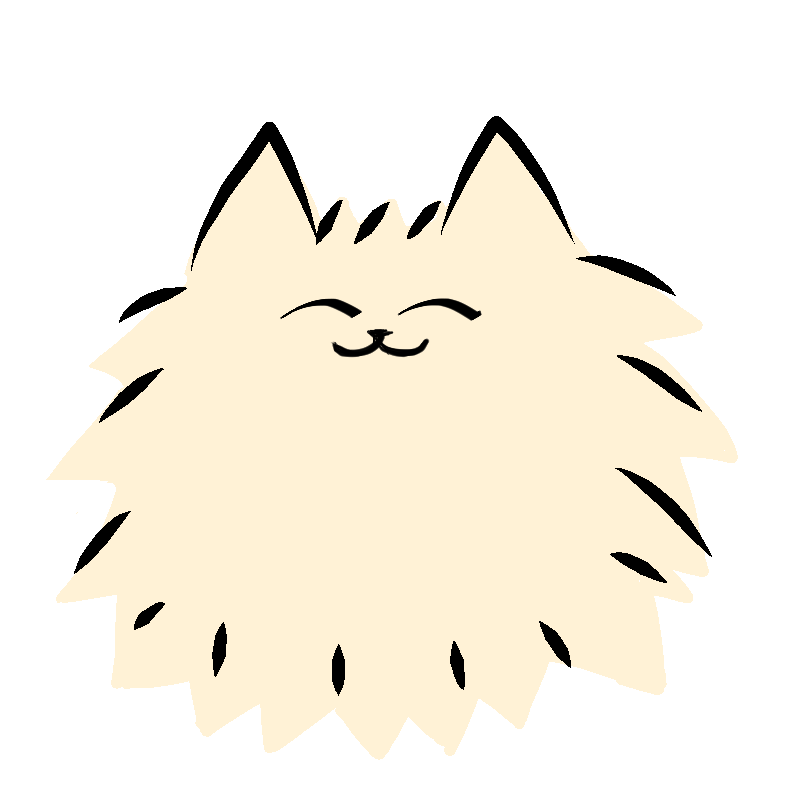
さいごまで読んでくれてありがと!番外編も読んでみて~
①お金でこまる原因を知る
├ お金が貯まる仕組みを作ろう
├ 家計簿が面倒なら『自動化』しよう
├ お金を貯めたいなら地銀はやめよう
└ FPおすすめのネット銀行3つ!ポイントは使い分け
②節約の仕組みをつくる
├ お金を貯めたいなら『最優先は節約』
├『固定費の見直し』住居費、通信費、光熱費編
├ 効果絶大!保険の見直し術
└ 節約の仕上げは変動費
③投資の仕組みをつくる
├ 投資初心者は『3つの基本』を押さえよう
└『不労所得』を手にするための『放ったらかし投資』←今回の記事