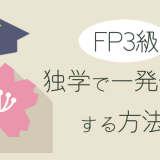は~老後が心配…ラクに億万長者になれんかな~~

強欲ッ…!
老後に備えるならイデコは一つの選択肢になるかもね。

イデコ?どーせなんか罠があるんやろ?

…無いこともないね…
2017年1月から公務員の加入もできるようになった「個人型確定拠出年金、通称iDeCo(イデコ)」。
各種メディアで「加入しなきゃ損!」とメリットばかりが取り上げられ、興味を持っている公務員さんも多いのではないでしょうか。
「早速加入しちゃうぞ〜」と資料請求したそこのアナタ!…ちょっと待ってください。
今回は、あまり語られないiDeCoの注意点・デメリットを紹介します。
選ぶ商品にかかわらず、iDeCoを利用するすべての方が関係する内容です。
特別法人税(年率1.173%)という罠の存在
さっそくイデコの注意点を。
- 積立金の全額に1.173%の特別法人税が毎年課税される
- ただし、2022年現在、課税は凍結されている

法人税?公務員個人なのに法人税かかるんか?

あんまり知られてないので、もうちょっと詳しく見ていこう。
特別法人税が与える影響
積立金全額に1.173%の税金が毎年かかります。
この「積立金全額」と「毎年」ってところがじわじわ効いてきます。
積立額は年々増えていくので、積立開始したばかりの頃と、積立終了間際ではかかる税金額に差が出ます。
積立額が増えるにつれて、取られる税金も増えていくということですね。
具体例でシミュレーション
- 30歳からiDeCo加入、月額1.2万円で積立開始
- 商品は元本保証タイプを選んだ
- その後、特別法人税の凍結が解除され、積立金に1.173%の税金を取られることに…
分かりやすくするために、手数料は無しで考えてみます。
凍結解除される時期によって、どんな影響があるのかグラフにしてみましょう。
積立開始後しばらくは減税額の方がかなり多い状態ですが、資産が増えるにつれその差は次第に縮まり、50代後半では逆転してしまいます。
元本保障タイプを選んでいたとしてもこれだけ取られちゃうんですね。
なお、上記グラフの減税額は所得税と住民税の合計額です。
所得税は30〜39歳まで10%、40〜59歳まで20%として算出し、住民税は一律10%としました。

にっくき特別法人税…
ではiDeCoはしないほうがいいの?
ここまで、ちょっと大げさにiDeCoのデメリットを書いてきました。
では、iDeCoはしない方がいいのか?
個人的には老後資金を効果的に準備したい人は、iDeCoを検討しても良いと判断してます。
理由は次の3つです。
- これまで1度も課税されてない
- ずっと撤廃が求められている
- 年利1.173%超えの運用を目指す
①これまで1度も課税されてない
iDeCoがスタートした当初から、特別法人税は凍結されており、これまでに1度も課税されたことがありません。
何度も凍結解除は先送りにされてきたんですね。
②撤廃が求められている
個人投資が促進される現代、iDeCoはキモになる制度です。
そんな中、特別法人税が課せられたら利用者は増えませんよね。
実際、金融業界から撤廃が求められてます。
今後、凍結解除となるのか、再び先送りされるのか、はたまた撤廃されるのか。このあたりは関連記事をお読みください。
③年利1.173%超えの運用を目指せば良い
特別法人税の税率を超える運用を目指せば良い、という攻めの発想。
iDeCoの運用益は非課税ですから、通常の証券口座で運用するよりもメリットがあります(通常は運用益の20.315%の税金が取られる)。
同様に税制優遇があるNISAと比較しても、優遇が受けられる投資総額や期間の制限がないため、iDeCoはより長期投資に向いた制度だと言えます。
一方、長期間で資金拘束されるデメリットもあるので、そこも含めて判断したいですね。
まとめ
今回、「特別法人税」をテーマにiDeCoについて書きましたが、この記事を通して僕が伝えたかったことはひとつです。
メリット・デメリットを把握し、自分の意思で決めよう。
iDeCoに限らず、投資にはリスクがつきものです。
資産が増えることもあれば、減ることもある。
その特性を理解したうえで主体的に投資するほうが、効果的な資産運用ができます。
重要なのは、一度は自分で考えてみて、判断を他人に任せっきりにしないこと。
この記事にたどり着いた方は熱心な方だと思いますので心配ないと思いますが、
もし周りに「よく分かんないけどおトクらしいし、確定拠出年金始めちゃおう」という方がいたら、「こういう注意点もあるみたいだよ」と教えてあげてください。
正直なところ、確定拠出年金に限って言えばメリットが上回っているので、おすすめしても「結果オーライ」になるケースもあるでしょう。
ですが、「自分で考えてみる」というワンクッションがあるのとないのとでは、損失時のダメージやリカバリーが違ってきますからね。